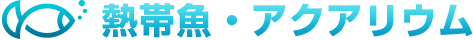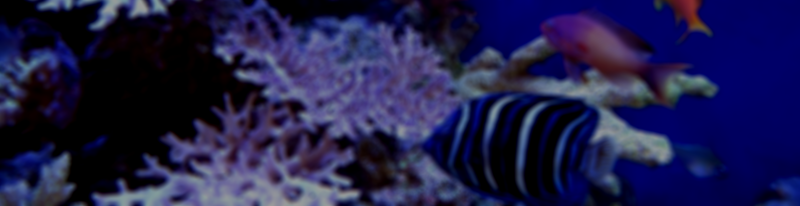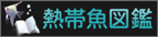“ボララス”ってどんなお魚なの??
ボララス属は東南アジアに分布するコイ科のお魚の一群で、わりとメジャーな小型熱帯魚の中では群を抜いた体の小ささが特徴です。あれ?と思った方も多いと思われますが同じくコイ科の中・小型種の“ラスボラ(魚の小さい奴)”と呼び名が倒置表現になっており「めっちゃ小さい魚」ぐらいの意味になっているとかいないとか。
ボララスの仲間たち

ボララス マクラートゥス Boraras maculatus
マレー半島やスマトラ島に分布。体側の大きな黒斑が印象的な種で記載されたのが1904年ということもあり、観賞魚関係のかなり古い書籍でもその姿を確認することができます。本属においては比較的大柄で派手さはないものの、その赤橙色の体色はなかなかに観賞価値の高いものです。最大サイズは25mmほど。

ボララス ミクロス Boraras micros
タイ東部メコン水系に分布。同属他種と較べて寸づまりなこともありグループ中でも実際かなり小柄に見えるお魚です。色彩的にはほぼ赤系統の本グループ内では異彩を放ち、透明感のある橙色のボディーに3つの小黒斑が入るというシンプルなもので、フォールスバルブやプンティウス・ゲリウスに似た雰囲気をもっています。調べてみた感じでは色彩に派手さがない・意外と深場にいて採集が面倒・・などの要因からか入荷頻度はかなり低いようです。最大サイズは15mmほど。

ボララス ナエブス“ミクロスレッド” Boraras naevus
タイ南部に分布し、かつてはボララス“ミクロスレッド”と呼ばれていたお魚で2011年に東南アジアのコイ科魚類に造詣の深いスイス出身の研究家であるマウリス・コテラット博士らによって上記の学名で記載されました。色彩・姿はミクロス種にはあまり似ず、むしろマクラートゥス種をキュッ!と縮めたような感じの強い赤橙色のお魚です。最大サイズは15mmほど。

ボララス ウロフタルモイデス Boraras urophthalmoides
タイ、カンボジアあたりに分布する本グループにおいては体高があり、わりとガッチリ体型のお魚。色彩は上記スポット系のボララスと違い、くっきりとした濃紺のラインが目立ち、そのラインの上部に橙色のラインがビシッと入るメリハリの利いたものになっています。入荷に際して同じくかなり小型の熱帯魚として有名なトリゴノスティグマ(ラスボラ)・ソンポンシィやオリジアス・メコネンシスが混ざることでも知られています。最大サイズは20mmほど。

ボララス ブリジッタエ Boraras brigittae
ボルネオ南部・インドネシアに分布する色彩・人気度ともに本属随一の美麗種。成熟したオス個体は真紅のボディーにメタリックグリーンのラインが入り、細身かつ小さい体ながらしっかりとした存在感のあるお魚です。若魚およびメス個体はこの柄がラインではなくスポット状に分割されているものも多いようで、後述のメラーと紛らわしいところがあります。最大サイズは20mmほど。


ボララス メラー Boraras merah
ボルネオ西部・南部に分布。透明感のある体に2つの黒斑が入る細身なお魚で、個体差が大きいものの長めの黒斑と黒点の組み合わせから『!』マークの入るボララスと認識される向きがあるようです。前述のブリジッタエによく似ていますがブリジッタエの尾ビレは上葉・下葉にクッキリと赤が入るのに対し、本種の尾ビレはそういった発色が無いことで判別できるようです。最大サイズは20mmほど。
飼育について
入荷時サイズも小さいため非常に頼りなさげに見えるのですが、実はほどほど育った個体の流通がほとんどなので、見た目に似合わない丈夫さを発揮することが多いです。コイ科小型種に共通する注意点として、慢性的な濾過不全や底床にエサの食べ残しやフンなどの過剰な有機物がたまっている場合に、白点病よりも治りの悪い『コショウ病』にかかりやすいので、濾過装置や底床のメンテナンスもしっかり行うと良いです。成魚は一般的なおとなしい小型種との混泳もギリギリ可能ですが、成魚クラスのプラティなどの大柄な個体がいる場合には若魚の導入は難しいと思われます。エサは口の大きさに合わせたものをチョイスすれば人工飼料でも良く食べます。また赤系のお魚が多いグループなので、高栄養かつ色揚げ効果の高い、ブラインシュリンプ幼生を与えるのもオススメです。
さて今回は結構人気の高い極小集団・ボララスの仲間を紹介しました。機会があればぜひ一度飼育にチャレンジしてみてくださいね♪